
山の日レポート
自然がライフワーク
【連載】地域とコラボ!里山再生⑤針葉樹皆伐跡地の広葉樹林化 ―20年の歩みと現在の到達点― (7/7)
2025.02.03
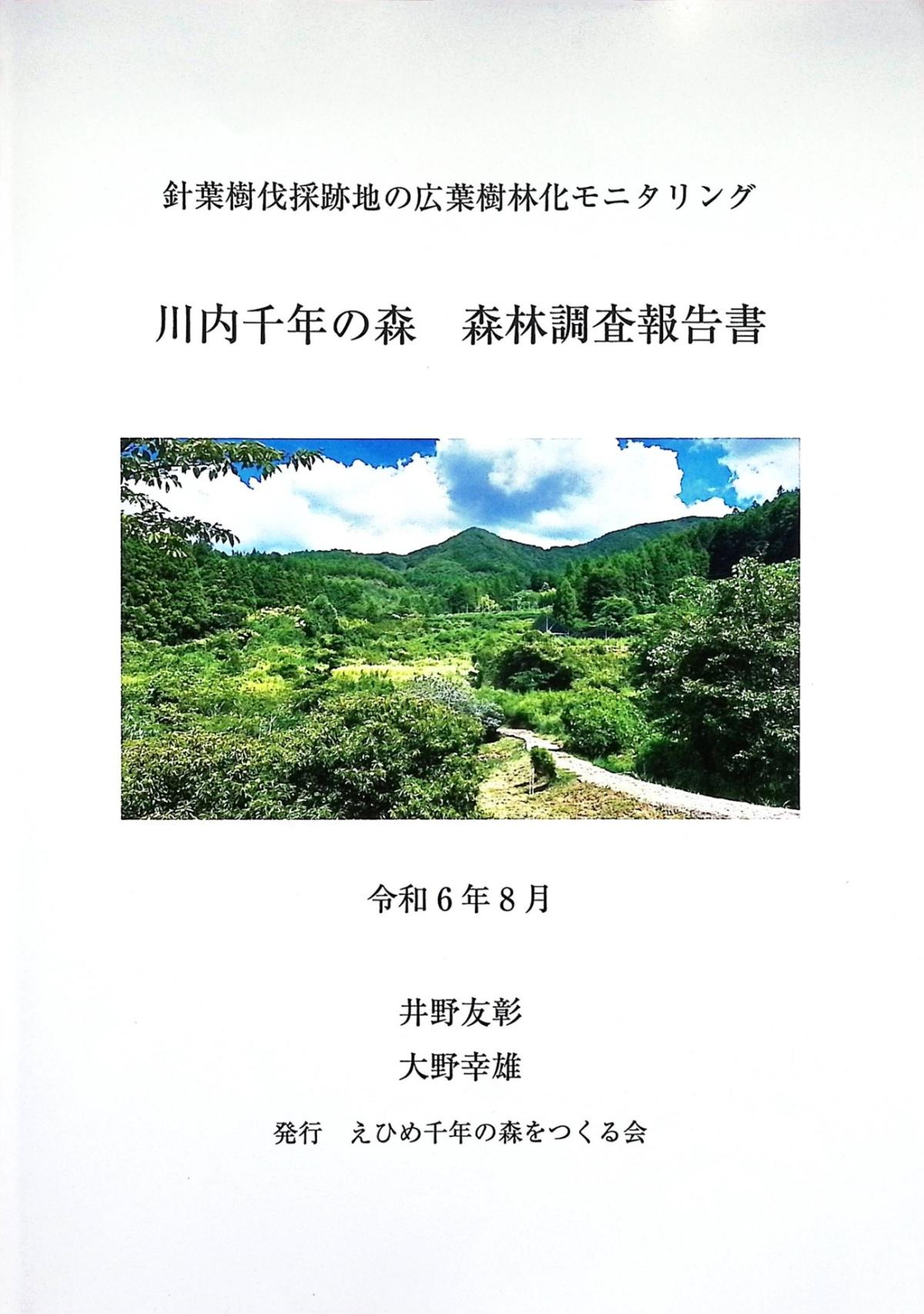
鶴見先生
「千年の森調査報告書」をお送りくださいまして有難うございました。
このようなものを長年にわたり育成し、その記録を継続しておられますことに心から敬意を表させていただきます。
記録を残していくことは何よりも大事なことだと思います。
全体に目を通して感じたことを率直に述べさせていただきます。
まず設計、植栽当初に、それぞれどういう森を目指していくのかという、大まかでも100~200年後ぐらいの「目標林型」を描くことが必要であったと思います。設計当時には、そういう考えが得られていなかったことはやむを得なかったと思われますが、大まかにでもそういうものは必要なことと思います。
設計にあたって、下刈り回数とその時期について十分に検討されていたか、とくに「蔓きり」計画は充分に計画されていたかなどの反省は必要だったように思います。
調査は、各層の植生優占度のような植物社会学的な組成の分析手法が用いられていますが、森づくりの立場からは、できれば「林分の発達段階」のような手法が望ましかったと思います。
以上は私の率直な希望的意見ですが、この調査報告はそれなりに、色々なことを考える材料となる価値のあるものだと思います。
なお、「はじめに」のところで、和暦が使われていますが、これは西暦にすべきだと思います。「千年の森」という超スパンの中で、和暦はなじみませんし、その後は全て西暦を使っていることとの整合性の上からもそれは必要です。
以上、率直な意見を述べさせていただきましたが、このような試みと、その調査資料は大変貴重なものだと思います。
藤森隆郎
日本が誇る世界的森林生態学者、現国民森林会議会長
1938年京都市生まれ。1963年京都大学農学部林学科卒業後、農林省林業試験場(現在の森林総合研究所)入省。森林の生態と造林に関する研究に従事。農学博士。研究業績に対して農林水産大臣賞受賞。1999年、森林環境部長を最後に森林総合研究所を退官。
国連傘下の持続可能な森林管理の基準・指標作成委員会(モントリオールプロセス)の日本代表、IPCCの執筆委員など国際活動を務め、IPCCのノーベル平和賞受賞に貢献したとして、IPCC議長から表彰される。
えひめ千年の森をつくる会会長 元愛媛大学教授 博士(経済学)
1946(昭和21)年茨城県生まれ
2001(平成13)年家族と愛媛県東温市井内の標高500mの棚田に移住、現在に至る。所有山林25ha 棚田1ha・15枚を所有し、未来循環型自給をめざした生活を営む。
大学在任中、えひめ森林ボランティア連絡協議会長、四国山の日実行委員会会長、四国の森づくりネットワーク会長を務める。
略歴
1978(昭和53)年:大学院を修了、千葉県の農業高校に22年間勤務。
間伐材の利用拡大や森林資源の炭化利用をテーマに、生徒とプロジェクト研究に励む。同時に社会人対象の学校開放講座を開き、炭焼き等を実施する。
2000(平成12)年: 愛媛大学農学部に移り、2012(平成24)年に定年退職。
新設された森林教育研究室を担当し、後に新設された農山漁村地域マネジメント特別コース長。
同時に、社会人対象の愛媛大学地域マネジメントスキル修得講座を担当。
2012(平成24)年:退職後、社会人対象の愛媛大学水産イノベーションスキル修得講座長。
おもな著書等
『日本林業成熟化の道』(分担)(日本林業調査会)1978年
『来るべき林業の時代に』(財団法人 富民協会)1988年
『エコロジー炭焼き指南』(監修)(創森社)1995年
『国際化時代と「地域・林業」の再構築』(分担)(日本林業調査会)2009年
『高等学校教科書森林科学』(分担)(実教出版)2022年
DVD環境教育シリーズ全5巻(監修)(紀伊国屋書店 2010年など

RELATED
関連記事など