
山の日レポート
通信員レポート「これでいいのか登山道」
【連載32】これでいいのか登山道
2025.04.25
連載32回目は、前回に引き続き登山道法研究会の重信秀年さんに、「春から夏の絶景を楽しむハイキング」と題してご寄稿頂きました。穂高や尾瀬などの著名山域で、山々を眺めながら歩く楽しみについてです。こうした行動を通じて、「よりよい山の道とはどういうものなのか」といったことも見えて来るのではないでしょうか。
皆様もぜひ、お住まいの地域や出かけた山々で感じたことなどを、ご寄稿くださいましたら幸いです(ご寄稿先メールアドレスは文末にあります)。
文・写真 重信秀年(登山道法研究会)

穂高や槍ヶ岳に登るのは「体力的にもう無理かな」と感じている人も夏になったら上高地に出かけて、大正池や岳沢湿原を歩いてみませんか。上高地の風景は青春時代と同じように美しいです。上高地には山小屋やキャンプ場が整備されているので泊まってゆっくり過ごすのもよいです。昼間の河童橋周辺は雑踏していますが、夕方や早朝は静寂そのもの。朝日が出る直前、穂高の峰々はバラ色に輝き、梓川の水面をただよう霧が晴れていく光景は幻想的で、自然の息吹にふれることができます。ただし、朝夕の森の道はクマと鉢合わせるおそれがあるため、ハイキングはほかの人たちも歩いている日中にしましょう。

上高地の焼岳を仰ぐ大正池の岸辺
尾瀬は純白の苞のミズバショウの群落で有名です。しかし、名曲『夏の思い出』の歌詞からイメージして真夏に尾瀬を訪れると、見ごろは過ぎています。ミズバショウは雪解けとともに苞を開くため、尾瀬ヶ原では例年5月中旬から6月上旬が盛り。そのころの尾瀬は、まだ肌寒く、湿原は枯れ草色。初めての尾瀬ハイクは、「梅雨明け十日」のころが過ごしやすくおすすめです。ミズバショウは大きな葉になっていますが、湿原は青々として美しく、サワギキョウ、ヒツジグサなど多彩な花が咲いています。鳩待峠までバスで行き、山ノ鼻に下って、竜宮十字路あたりまで木道を往復するとよいでしょう。

燧ヶ岳を眺めながら尾瀬ヶ原の木道を進む
次に案内する絶景ハイキングコースは、岐阜県可児市の鳩吹山。木曽川の岸にそびえ、「日本ライン」と呼ばれる渓谷を形づくっている山です。標高313メートルの低山ですが、山頂からの眺望は素晴らしく、天気がよければ、御嶽山、中央アルプス、さらには乗鞍岳や白山まで見える大展望。カタクリ口コースから登ると岩場の道もあり、短時間ですが登山気分を満喫できます。眼下の木曽川の右岸、美濃加茂市の旧中山道太田宿の寺に槍ヶ岳の開山者、播隆上人の墓があるので、登山家は下山後に参ってみてはいかがでしょう。鳩吹山の注意点を一つ、休憩舎を含めて火気厳禁のため、調理用コンロは使用できません。

鳩吹山から木曽川を望む。遠くの山並みは中央アルプス
今回は最後に、首都圏に住んでいる人が出かけやすい低山のハイキングコースを『奥武蔵・秩父ベストハイク30コース』という別の本からご紹介します。「埼玉県に絶景があるの?」と思うかもしれませんが、埼玉県の西部、飯能市、秩父市、越生町、東秩父村あたりの里山の春から初夏の景色は美しく、「日本のふるさと」といった風情です。例えば、西武池袋線の吾野駅で下車して、顔振峠に登り、風影や八徳といった山の集落をめぐっていると、路傍に野の花がたくさん咲いていて、良寛さんの「鉢の子にすみれたんぽぽこき混ぜて三世のほとけに奉りてむ」という歌が思い出されたりして、心が洗われるようです。

顔振峠の摩利支天堂から風影の集落や武甲山の眺め
『絶景ハイク 関東・中部33コース』
著者:重信秀年
発行:東京新聞
発行日:2025年3月25日
定価 1,650円(本体1,500円+税10%)
『奥武蔵・秩父ベストハイク30コース』
著者:重信秀年
発行:東京新聞
発行日:2023年3月31日
定価 1,540円(本体1,400円+税10%)
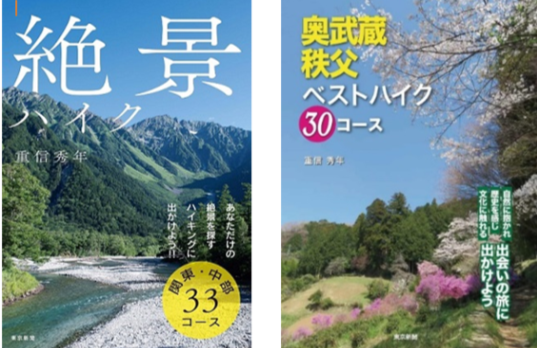
登山道法研究会では、これまでに2冊の報告書を刊行しています。こちらは本サイトの電子ブックコーナーで、無料でお読み頂けます。
https://yamanohi.net/ebooklist.php
また、第2集報告書『めざそう、みんなの「山の道」-私たちにできることは何か-』につきましては、紙の報告書をご希望の方に実費頒布しております。
ご希望の方は「これでいいのか登山道第2集入手希望」として、住所、氏名、電話番号を記載のうえ、郵便またはメールにてお申し込みください。
●申込先=〒123-0852 東京都足立区関原三丁目25-3 久保田賢次
●メール=gama331202@gmail.com
●頒布価格=実費1000円+送料(430円)
※振込先は報告書送付時にお知らせいたします。
報告書の頒布は、以下のグーグルフォームからも簡単にお申込み頂けます。
報告書申し込みフォーム
先に刊行致しました「第1集報告書」は在庫がございませんが、ほぼ同内容のものが、山と渓谷社「ヤマケイ新書」として刊行されています。
ヤマケイ新書 これでいいのか登山道 現状と課題 | 山と溪谷社 (yamakei.co.jp)
また、このコーナーでも、全国各地で登山道整備に汗を流している方々のご寄稿なども掲載できればと思います。
この記事をご覧の皆さまで、登山道の課題に関心をお持ちの方々のご意見や投稿も募集しますので、ぜひご意見、ご感想をお寄せください。
送り先=gama331202@gmail.com 登山道法研究会広報担当、久保田まで
RELATED
関連記事など